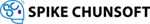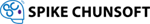――特別な人に、特別なものを。
俺が進むべき道を見つけたのは、そのことを意識し始めてからだと思う。
(最初は、バイト先のお客が、料理を美味しいと喜んでくれたのがきっかけだった)
それならもっと美味しいものを作ろうと思った。
次はもっと美味しいものを。
その次は、もっと――
(希と同居して、俺の作った食事を食べてくれるようになったのが二つ目のきっかけで)
最初は希も渋々といった様子で食事に手を着けていた。けれど一度も残すことはなかったし、月日が経つにつれ食べる様子も変わり、『ウマい』ともらすことさえあった。
(そして、次は)
クリスマスに作った、マカロンだ。
クリスマスという口実があるのだから、彼女に何か渡そうと思った。
ただ、最初考えていたのはマカロンではない。
出来れば形に残るものがいいだろうと思い、ショッピングモール、商店街、駅前の店、色々な店を見て回った。
――例えば、服。
彼女に似合う服はと考えると、どの服でも似合うような気がしてくる。
かといって店員に聞くのもためらわれ、結局諦めてしまった。
――例えば、アクセサリ。
彼女は大げさなものは好まないだろう。
あまり値段が張らず、小ぶりなアクセサリならばいいのではないか。
ネックレス、ブレスレット、あるいはピンキーリング……とまで考えて、手が止まった。
付き合ってもいないのにアクセサリをもらっても、あいつなら困って返してくるんじゃないだろうか。
お前のために買ったんだからと言っても、遠慮をするか、同等のものを返そうとしてくるんじゃないだろうか。
そう考えるとこれもナシだ。
――小物、花、本、ぬいぐるみ、文房具。
どれを候補にあげても、結局は同じところに突き当たる。
彼女がどれを喜んでくれるのか分からないし、今それを贈ったところで受け取ってもらえるかどうか。
俺の気持ちとしては、どんなものだって彼女が喜んでくれるのならば贈りたい。
(特別で、大切な人だから。想いを込めて贈りたい)
そこまで考えてから、ふと。
でもそれなら、もっと特別な……二つとないものの方がいいんじゃないか、と思った。
(あいつがもっと気軽に受け取れて、その上で俺の想いを込められるとしたら)
菓子を作ってみるのもいいかもしれない、と思った。
(手作りの菓子を誰かに贈るなんて、獅子吼じゃまず見ないな)
自分の考えに自分で笑ったが、『獅子吼生らしさ』よりも彼女へのプレゼントを特別にすることの方が大事だと気付く。
身近に希という俺の料理を喜んでくれる人間がいるから、確信出来る。
(付け焼き刃のプレゼントより、自信がある。どれを選んでいいのか分からない服やアクセサリや小物よりは)
磨いてきた腕も、彼女のために使えるのならば、それほどうれしいことはない。
結果、俺はクリスマスプレゼントとして彼女にマカロンを作ることにした。
(特別な人に、特別なものを)
そして、大切な誰かに美味しいと言ってもらうために、菓子を作ることが出来るのならば。
パティシエになるのもいいと思った。
つづく

カシャカシャとメレンゲを泡立てながら、俺はマカロン作りの工程を頭の中で反芻する。
(メレンゲを入れ、粉類を加え、マカロナージュ……つやが出たら絞り袋で絞り、ピエが出るまで焼く)
レシピはいくつか参考にして試作し、今回はそれを総合しベストと思える材料配分と手順を採用した。
(メレンゲはこんなものか。次はあらかじめアーモンドパウダーと粉砂糖を混ぜておいたものを入れて、メレンゲを潰さないように……)
「……兄貴?」
「…………」
「おい」
「…………」
「おい!」
突然近くで大きな声がして、ボウルから目を離す。
そこには呆れた顔の希がいた。台所いっぱいに広げられた調理器具を眺めるようにして、ため息を吐く。
「全然気付かねぇとか、すげー集中力だな」
「すまん。手順を考えていて」
「別に謝んなくても……外行くけど買い物あるかって聞こうと思っただけだし」
「ああ、助かる。じゃあ卵を頼む」
ぶっきらぼうに分かったと返しつつも、希はじろじろと俺の手元を見た。
「またマカロン作ってんのかよ。この間も作ってなかったか?」
「それは試作だからな。納得出来るまで練習したいんだ」
「へー……」
今ひとつ理解出来ないという様子だったが、希は俺の手元を一瞥し行ってしまった。
(……まあ、これまでこんな風に菓子作りに没頭したことはなかったしな)
先人の知恵が詰まったレシピ通りに作れば、料理も菓子もそう失敗することはない。
しかし特別な菓子を作るのは難しい。
想いを込めれば込めるほど、もっと良い物にならないかと考えてしまう。
(砂糖を減らすか。それともいっそ別の味のマカロンにしようか、甘酸っぱい柑橘系か、香ばしいナッツ系……いや、やはりこのままいこう)
彼女のうれしそうな顔を見たいから。
特別な笑顔が欲しいから。
(鈴風で初めて出会ったころと、今と……真っ直ぐな笑顔は何も変わらないが)
彼女は俺をお兄ちゃんと呼び、全力で信頼を置いてくれていた。
格闘技を教えるたびに目をキラキラさせて、ちょっかいをかける奴らを遠ざけるたびに安心した顔で俺のそばにくっついていた。
(それ以上の、笑顔が欲しい)
彼女と過ごした時間はそれまで過ごしたどんな時間よりも愛おしく、大切な時間だ。
あんなにも誰かを守りたいと思ったことはなかったし、誰かを信じ頼られたいと思ったのは初めてだった。
そして誰のことも信じられない、信じたくないと思う俺の人生の中で、彼女だけが輝き、希望になった。
この希望さえ胸にあれば、多少の苦難なら乗り越えていけるとさえ思えるほどに。
(俺にとってあいつは特別な存在だから)
だから俺はあいつにとっての『特別』でありたい。
(あいつが……好きなんだ。誰よりも)
その想いがどこまで伝わったかは分からない。
クリスマス当日まで俺は試作と練習を重ね、手作りのマカロンを完成させた。
彼女はそれを笑顔で受け取ってくれたし、結果昔のように手を繋ぎ歩くことも出来た。
そんな特別な経験が、俺を変えてゆく。
(あいつのことも好きだし、菓子を作ることも好きだ)
彼女に製菓の腕を褒められると、これ以上ない喜びを感じる。
俺が今まで積み重ねたものを認めてもらえるのがうれしかった。
そして気が付く。
(これからもこんな風に、誰かに菓子を食べてもらいたい)
いつしか俺は、本気でパティシエになりたいと考え始めていた。
つづく

だというのに。
(もっと成長しろとでも言いたいのか)
学校の屋上で右手を見つめながら、自分の不運を恨む。
その手はまだ腫れて変色しており、今は包帯で固定していた。
このケガを負ったのはつい先日のバレンタインのことで、たまたまチンピラに絡まれたのが運の尽きだった。
たくさんの菓子を持っていたので上手くやり過ごすことも出来ず、手首を捻挫してしまった。
就職先として紹介してもらったレストランの実技試験を再来週に控えた今、手をケガするのはきつい制約だ。
(とはいえ、落ち込んでいても仕方が無いしな)
思い直し、昼食にと用意していたパンを食べようとすると、その袋を横から取り上げられた。
「未良子」
名前を呼んだ俺を気にも留めず、未良子はパンの袋を開けて手渡してくる。
どうやらケガをしている俺を気遣ってくれたらしい。
「……何か裏でもあるのか」
「ええ? パンの袋開けたくらいで恩に着せたりしないって。オレのことなんだと思ってるの」
「未良子だと思ってる」
「ひどすぎ」
「……まあ、気遣いには感謝する。袋くらいは開けられるが」
開けてもらったパンを咀嚼する横で、同じように未良子もパンを食べ始める。
「でも、なるべく安静にしないとね。早く治すためにもさ。もうすぐ試験あるんでしょ?」
「知ってたのか。事前に進めていたから準備はそれなりに整っているし、心配するほど重症じゃないと思っている」
「そう言いながら、さっきケガした手見ながら憂鬱そうにしてたじゃん」
見られていたのか、と思い軽く目を伏せる。
(まったく。これだから未良子は)
すぐ俺の心を見透かしてくるから、困る。
「……憂うくらいはする。だが不安に囚われていると、気を遣ってくる奴がいるからな」
憂いを重ねた答えに、隣の未良子が楽しそうに肩を上下させた。
「ふっ。相変わらず仲いいねー」
それには答えずにいると、ペットボトルの水を飲みながらさらに未良子が笑う。
「最近一緒にいるところを見なかったから、別れたのかと思ったけど。気のせいか」
「……付き合ってない。まだ」
まだ、という言葉になおさら笑い声が大きくなる。
「はいはい、牽制牽制。麟太郎は大好きオーラ丸出しなのに、よく気付かないよね~あの子も。好意が溢れて暴走しないよう気をつけてね。前みたいにさ」
「……気をつけるようにはしている。行き過ぎると良くないと、他でもない本人に諭されたからな」
獅子吼に残って彼女を守るために留年しようとした俺を、『誰かを守るために自分を後回しにしないで欲しい』と止めたのは、他でもない彼女だ。
その一言は、そうすればずっと一緒にいられる、万一の時にも彼女を守ってやれると思っていた俺の目を覚ました。
(あいつは十分強くなった。あいつを信じ、俺自身の道もちゃんと歩んでいくことこそが……大切なことなんだろうな)
それからは、適切な距離を保つようにしている。
少なくとも、獅子吼の中では。
未良子が最近一緒にいるのを見ないというのもそのせいだ。
そんな風にしてこれまでを反芻していると、携帯がメール受信を知らせた。
つづく

「え、何? 愛しの彼女からのメール?」
「うるさい」
図星だったのでそうとしか言えず、中を確認する。
内容は、週末についてだった。
『試験対策がだいたい出来ているのなら、土曜を詰めの日にして日曜は出かけませんか? 気分転換も大事だと思いますし、手を休めた方が良いですよ! 私が使わないように見張ってますから』
見張るという言い方が面白く、笑ってしまう。
手をケガしてからというもの、試験対策の菓子作りは希や彼女に手伝ってもらっていた。今週末にしても同じだと思っていたが。
(でも……そうだな、気分転換も必要かもしれない)
言い分はもっともだと思い、『わかった』と返信しておく。
そして顔を上げると、未良子が横からそれを覗き込んでいた。
「覗くな」
「へー。ほんっっっとに仲いいんだね。夫婦ってカンジ」
「うるさい」
「でも行き過ぎっていうのも自覚したみたいだし、麟太郎に余裕が出来て良かったよ」
その一言には正直返す言葉がない。
大概のことには冷静に、俯瞰して対処出来るつもりでいたのに、彼女のこととなると別で。
(冷静になれない自分を思い知らされるな)
返事をせずにパンを頬張っていると、未良子の追撃が入った。
「で、いつになったら付き合うの? 告白はいつ?」
「ぶっ」
つい噴き出す。なんていうことを聞くんだと辺りを見回すが、屋上には他に誰もいない。
「お前に言うわけないだろ」
「いーじゃん別に。牽制するなら思い切ってしようぜ。じゃないとオレもあの子を弄りにいっちゃうよ~?」
「やめろ。手が出る」
「ケガしてんのに?」
「うるさい」
本当に人をからかうのが好きな奴だ。
彼女が女だということを知っているのは獅子吼では俺と未良子だけだろうし、危機感はある。
だから何度も牽制をしているというのに。
「お前が本気だというなら仕方ないが、ケガが治ってからにしろ」
「……治ったらどうすんの?」
「タイマンするに決まってる」
「あっははは」
またこの笑い声だ。
半分冗談だろうと思ってはいたが、冗談じゃない可能性が一パーセントでもあるなら同じことだった。
「本気で行くからな。手加減はしない」
「やだな、麟太郎の思い出の子に手ぇ出したりしないって。勝てない戦いを挑むつもりもないしね」
幾分か声の調子を和らげ、そんなことを言う。
「勝てない戦い、か……」
「……明らかにそうでしょ。見てて分かんない?」
これにも沈黙してしまう。
未良子がどういう意図で言っているのか把握しかねるが、悪い意味ではないように思う。
「本気で俺が勝てると思うか?」
「それオレに聞くぅう~? ……勝てるでしょ。条件付きだけど」
「条件付き?」
「この間みたいにおかしな暴走しないこと。ちゃんと自分で立って、前に進んでる麟太郎があの子は好きなんじゃない」
まあ好きになっちゃった後なら関係ないかもしんないけどと付け加えつつ、未良子は昼食に戻る。
苦笑いしながら、頷いた。
「それは……分かってるつもりだ。だから夢をつかむまでは何も伝えないつもりだし」
「ああ、なるほど。それで我慢してるわけだ」
「……我慢……」
「してるでしょ」
深いため息になる。
こいつはどこまで見透かしてくるのか。
(確かに我慢と言えば、我慢なんだろうが)
好きだと言いたい。
他の男に目を向けないでくれと言って独占したい。
自分だけの、特別な人になって欲しいと言いたい。
その気持ちをずっと抱えながら、そばにいる。
時に自分でも醜いと思えるほどの感情を、いつも抑えていた。
けれど最近になってようやくそれが和らいだ、その理由は。
「――目指すところが、決まったから。パティシエを目指そうと思ってからは、少し変わったと思う。我慢はしているが……それもお互いのためだと思い、パティシエになるための力に変えることが出来るようになったのかもしれない」
ちゃんと夢をつかんで、それから彼女に告白をしたいから。
そう思うと我慢は我慢ではなく、未来のために踏むべき手順だった。
「なるほど。ずいぶん前向きだねー。ケガにしても、あの子のことにしても。それに……」
「……それに?」
ニヤニヤとした顔でこちらを見る未良子に尋ねると、なおも笑って言った。
「めちゃくちゃ素直~!! やっべぇ麟太郎が素直すぎてカワイくなってる~」
爆笑する横腹に蹴りを入れ、その日の昼食は終わった。
つづく

「今日はやんねぇの、アレ」
朝早くに起きて着替えていた様を見て、希がそう問いかける。
「『アレ』?」
「菓子作り。試験対策は終わったのかよ?」
「ああ、だいたいはな。だから今日は休みだ」
そう答えながら、つい顔が緩む。
昨日は彼女と二人で菓子を作り、来週の試験へ向けて最終の確認をした。
そして今日は気分転換ということで、朝から一緒に出かけることになっている。
(デート……と思うのは俺だけだろうが)
思わず早朝に目覚めてしまうくらいには気分がよく、楽しみだった。
おかげで身支度にはいつもの倍時間がかかり、希にも怪訝な顔で見られた。
それでもうれしくてたまらない。
「ま、最近ずっと根詰めてたし。たまにはいんじゃねえの」
鏡を確かめて家を出ようとすると、希が意外にもそう言った。
「……そう思うか?」
「そう。兄貴は真面目すぎなんだよ。何でもかんでも一直線で……余裕持つのも大事だからな。試験とかはさ」
年下の希にそう言われるのはなんだか可笑しくて、口の端を上げる。
「ありがとう。心配かけたな」
同時に、希の口から俺を気遣う言葉が出たことが喜ばしかった。
去年の春あれほど遠かった距離が今は嘘のようだ。
「べ、別に心配なんかしてねえよ!」
分かりやすい照れ隠しをする希に、追い出されるようにして家を出る。
一年で、俺を取り巻くすべてが変わった気がする。
とてもいい方向に。
(――全部、あいつのおかげだ)
待ち合わせは普段は行かない、遠くの駅と決めていた。二人で出かけようと話した時に候補になったのが動物園だったので、その最寄り駅だ。
わざわざ遠くの駅を選んだのは、獅子吼の生徒を避けるために他ならない。
二人でいるところを獅子吼の生徒に見られて万一詮索されても面倒だし、何より――
(この姿が、見たかった)
「吉良先輩! 早いですね」
小走りに駆け寄って、彼女が待ち合わせ場所に到着する。
その姿はいつもの『鬼ヶ島ひかる』ではなく、本来の女性としての姿だった。
(……お前はそういう服を着るんだな)
髪をピンで留め、女物のコートにタイツ、ブーツを履き、毛糸の手袋をつけている。ところどころに見えるパステルカラーの色合いも明るく、普段とは全然違う。
(わざと女らしい服装を選んでくれている……なんて思うのは、さすがに自惚れか)
「楽しみで仕方が無かったから早く着いたんだ。その服、可愛いな」
俺の発言に面食らったようで、彼女は一瞬固まり、直後困ったように自分の格好を見回した。
「これ……変じゃないですか? 女の子の格好ってどういうのがいいか、すごく悩んだんですけど」
「可愛い。似合ってる」
正直、どんな格好であっても同じことを言ったとは思う。
それでも悩んで服を選び、俺に会いに来てくれたことがうれしい。だからその気持ちのすべてを一言に込めたつもりだった。
すると今度ははにかんで彼女は笑う。
「ありがとうございます。先輩もその服、格好いいです!」
動物園に入りパンフレットを見ながら話すが、その間もずっと彼女の声は楽しげに弾んでいた。
「やっぱり冬場は動物園も空いてるんですね」
今日の目当てはペンギンの行進と冬毛の動物で、冬場ならではの展示があると聞いた。
なんでも『氷の城』があるらしいが、それがどんなものかは分からない。
「寒いからな。お前は大丈夫か?」
「はい! 防寒対策バッチリです。使い捨てカイロもたくさん……あっ」
俺に見せようとしたのか、その勢いでカイロがボタボタと落ちる。
拾い上げ手渡そうとすると、そのうちの一個を押し返された。
「吉良先輩も一個どうぞ。あったかいですよ」
「いいのか?」
「わたしは五個持って来ちゃったので……多すぎました。今暑くって」
手袋を外して扇いでみせるので、強がりではないのだと分かる。
ありがたく懐に入れつつ、ふと。
「そんなに暑いのか」
その手を軽く握ってみる。
え、と言って目を見開き、頬を赤くする様が可愛らしい。握った手も温かく、こちらまで赤く染まっているように思える。
「本当だな。熱い」
「……吉良先輩の手、冷たいですね」
「手袋をすると着脱が面倒だからな。片手は使えないし」
「じゃ、じゃあ! わたしが温め……ます……!?」
勢いの発言だったのか、自分で言いながらしまったという顔になるのが面白い。
(温める、か。手を握るくらいしか思いつかないが)
さほど期待はせずに、少しからかうような調子で繰り返してみる。
「じゃあ、温めてもらうかな」
すると一度は躊躇したものの、結局彼女は俺の手を握り直して言った。
「はい。繋いだまま、行きましょう」
わずかに動揺した俺を、温かな手で先導してくれる。その髪の隙間から、赤く染まった耳が見えた。
思わぬ形で希望が叶い、こちらも驚きが隠しきれない。
(いつも俺から繋いでいたのに。昔も、今も)
去年のクリスマスの際、適当に理由をつけて手を繋いだことを思い出す。
昔を思い出しながら並んで歩く時間は、心地よく、幸福で、俺を満たしてくれた。
(でも今は……もっと幸せだ)
恋人同士でもなく、ただの勢いだったとしても。
自分の意思で俺の手を握り温めてくれるその優しさが、何よりの幸福だった。
つづく

自動販売機で飲み物を買って戻ると、彼女は飽きもせずにペンギンを眺めていた。
冬毛のリスやプレーリードッグを見た後、ペンギンに辿り着いてからもう二十分にもなるだろうか。
「可愛いなー、ほんとに」
手すりに身体を預け、しみじみと呟く。
可愛いのは彼女だと思うが、同じように手すりに寄りかかり視線の先を探した。
「子供のペンギンか」
「モコモコしていて可愛いですよね。お城が気に入ってるみたいで、さっきから何度も出たり入ったりしてるんですよ」
『冬場ならではの展示』とは、ペンギンのエリアに今だけ設置されている氷の城のことだった。
氷で出来た城はこじんまりとしていてペンギンが入れるギリギリの大きさだったが、彼女が言った通りペンギンたちが出入りし、その様はなかなかに面白い。
周りの客からも声が上がり、写真を撮る音が聞こえた。
「歩くだけで愛嬌があるというのはすごいな」
「ふふ。おかげで飽きません」
動物園を満喫する彼女の手に、買ってきたばかりの温かい飲み物を渡す。
それを受け取ると、瞬きしながら俺を見上げた。
「ありがとうございます。これ、いくらでしたか?」
「今日は気にするな。さんざん試験対策に付き合ってもらった礼もしたいし」
「その分、作ったお菓子をいっぱい食べさせてもらいました」
「それは礼にならないだろ」
俺が微笑すると、彼女も肩の力が抜けたように笑顔になる。
「なりますよ。……でも、これはありがたくいただきますね」
「そうしてくれ。そろそろ手も冷たくなってきただろ」
「だんだん吉良先輩の手の方が温かくなってきたかもって思ってました」
俺は繋いだ手の温度の変わりようも楽しんでいたが、彼女は気にしていたらしい。
「お前の手が冷たくなったら、今度は俺が温めるから」
「あ、あはは……じゃあ、お願いします」
手を繋ぎ続けることも照れくさいのだろうに、彼女は頷いてくれる。
「……お前は……」
「え?」
「いや」
その健気な仕草を見て、つい口から出そうになった台詞を呑み込んだ。
(お前は、手を温めるという口実がなくても、俺と手を繋ぎ続けてくれるのか)
しかしそう尋ねたところで、彼女が困るだけだ。
(理由なんて用意しなくとも、ずっと手を繋いでいられたらいいのに)
距離を詰めすぎないように。
夢をつかむまでは、黙っておくのだから。
彼女が困らないように、わきまえないと。
分かってはいるが。
(我慢――我慢、しているな。こんなにも)
自分の中に目覚める衝動を飼い慣らすのに苦労する。
(お前が好きだと、言いたい)
悔しいが未良子の言う通りだ。
自分で言ったことを撤回してしまいそうなほど、彼女の一挙一動で心が揺れ動く。
(俺の気持ちを聞いても、お前は喜んで受け入れてくれるんじゃないか。そう、思ってしまう……それは大きな勘違いで、思い上がりかもしれないのに)
けれど、いや、それでも、と何度も心の中で葛藤する。
「あ!」
そんな時、突然彼女が声を上げ、俺が持っていた缶コーヒーを取り上げる。何かと思えば、おもむろにその缶の蓋を開けた。
「手。使っちゃダメですよ」
「……そうだったな」
飲み物で身体を温めてから、俺たちはまた手を繋いだ。
つづく

ペンギンの行進を見た後は、冬毛のニホンザルを見ることにした。
こちらは室内から眺めることが出来たので、温かい部屋の中からゆっくりその姿を見守る。
冬場の彼らはたっぷりとした美しい毛皮に覆われており、まるでぬいぐるみのようだった。仲間同士で身を寄せ合って暖を取っている姿も微笑ましい。
「あそこの親子、ずっと同じポーズしてますね」
「抱き合って頬を寄せて……あれが一番温かいんだろうな」
「そうなんでしょうね。可愛い」
普段彼女があまり口にしない『可愛い』という単語も、今日ばかりは何度も聞くことが出来る。
取り繕うことのない、本音なのだろうと思う。
「去年一年間の記録、なんてのも流れてるな」
室内に設置されていた画面には、四季の移り変わりとともに彼らがどう過ごしていたかの記録が映し出されていた。
ちょっとしたドキュメンタリーになっており、サルの日常生活や出産、中には亡くなったサルについてのエピソードもある。
『ユキは九月に息を引き取りました。最期のお別れの際、仲間たちは彼女を囲んでしばらくその様子を見ていましたが、やがて離れていきました。その中で母親であるヒナタと妹のアメだけは、ユキから離れず、ずっと一緒に居ようとしていました』
それを観た彼女は、あ、と声を上げた。
そしてガラス越しのサルの親子と映像を見比べて指を指す。
「あの仲良く寄り添っている親子、この映像の親子ですね。ヒナタとアメ……」
「そう、なのか? 見分けがつかないが」
「小さくて分かりにくいけど、ヒナタの口にケガの跡があります。抱き合ってる格好も同じ」
なるほどと納得する。
言われてみればその通り、確かに目の前の親子と画面の中の親子は酷似していた。
画面の中の過去とガラス越しの現在とを交互に見て、彼女は寂しげにぽつりと呟く。
「じゃあ、亡くなったのはヒナタの子供で、あの子のお姉さん……」
映像のナレーションはなおも続いた。
『ヒナタは職員の手からユキの亡骸を奪うと、抱きかかえて離しませんでした。妹のアメも、その身体を温めるように寄り添っていました。サルはこんな風に、仲間の死を認識出来ず数日を過ごすことがあります。二匹がユキの死を認めた後、職員皆でユキを弔いました』
ヒナタがユキの亡骸を抱えたまま、あちこちを行ったり来たりする映像が挿入される。
子供が亡くなってなお戸惑い続けている姿は痛々しい。それを観ていると、いかに彼らが家族を大切に思っているかが伝わってくる。
「……サルは、思っていた以上に愛情深いんだな」
「そうですね……」
亡骸を抱えて右往左往する様を、愚かだとは思わない。
むしろそこに愛情を見出し、胸を打たれた自分に自分で驚く。
(昔の俺は、ここまで感情移入することは出来なかった)
対象が人間ではないからというわけではなく、家族の間に存在する愛というものに興味がなかった。理解出来る気もしなかった。
無償の愛など覚えがないし、血の繋がりはイコール絆ではない。
けれど、今なら心に染みる。
(大切な時間を共に生きたもの同士に、生まれる絆もあるのだろう)
それは例えば隣にいる少女と自分を繋ぐものの一つだと思う。
(俺たちは家族から縁遠い施設で出会ったし、家族愛というものもずっと自分には縁のないものだと思っていたが……今は、違う)
自分の心境の変化を噛みしめる。
希は血が繋がらなくとも俺の弟だし、隣にいる彼女になら俺は無償の愛を注ぐことも出来る。
かつて俺が遠ざけていた愛情というあやふやなものに動かされる人間に、いつの間にか俺自身がなっていたのだ。
(不思議だな……)
改めてそう思っていると、隣から小さな声が漏れ出る。
「……っ」
見れば彼女は唇を引き結び、溢れる感情を堪えているようだった。目に涙がたまる。
その表情から察するに、目の前の光景を見て俺以上に思うところがあったのかもしれない。
「……泣いても、構わないが」
我慢しているように思えてつい言うと、朗らかな笑みが返って来る。
「はい」
はいと答えたが滲んだ涙を拭い、深呼吸をしてまた映像に没頭する。
(これまでずっと人前では鬼ヶ島ひかるとして気を張っていたのに、今は――きっと、本来のお前なんだよな)
動物たちの愛情に涙を浮かべる姿は、獅子吼生の前では見せないに違いない。
それどころか、他の人間の前では見せないようにしている姿かもしれない。そう思うとそれだけで優越感が満たされていく。
(俺の前でだけ、泣いてくれればいい)
俺の中にある彼女への思いが、どんどん自分勝手になっていくのが分かった。
つづく

昼食は園内でハンバーガーを食べることにする。
ハンバーガーなら片手で食べられるのでありがたい。そう思っていたが、このハンバーガーがくせ者だった。
(思ったより具が多くて、こぼれる)
片手ではカバーしきれず、テーブルに食べかすが落ちてしまう。どう努力しても無駄だった。
早く食べて拭いてしまおうと思っていると、俺の向かいに座っていた彼女がイスを持ってきて隣に座り直す。
そして食べていたハンバーガーに手を添えて、楽しそうに『どうぞ』と言った。
「どうぞって……それじゃほとんど食べさせてもらってるようなものじゃないか?」
「いいじゃないですか。手を休めるって言いましたし」
「……それは、そうだな」
彼女がそう言うならと大人しく従うことにする。
「はい、どうぞ!」
こぼれないよう両手でハンバーガーを包み込むようにして、俺に差し出す。
さっきより遥かに食べやすい。が。
(これは……さすがに)
まるで子供扱いを受けてるようで恥ずかしい。
俺が食べている様子を、彼女がじっと目の前で見ているせいもある。一口や二口食べさせてもらうのとは訳が違う。
「あ、飲み物も飲みますか?」
置いてあった飲み物にストローを挿し、口元に運んでくれる。こうなるともう笑ってしまった。
「くっ、くくっ……それじゃ介護じゃないか?」
「う……それはそれでいいじゃないですか」
「いいのか? 俺は介護じゃなく――」
「ほら、恋人同士でも『あーん』ってしますし!」
俺が言おうと思ってやめたことを口にするので、戸惑い黙る。すると彼女もはっと動きを止めた。
「そうだな。それなら介護じゃない」
「で、ですよね……」
「じゃあ今日は、お前に任せる。俺は……嫌じゃないから」
「そ、そうですか」
今度は彼女の方が照れながら、食事を続けていく。
(お前がやりだしたことなのに、自分で赤くなって……それでも最後まで続けるのは、性格だな)
動物園を堪能し、日が少し傾いてきた頃。
彼女は両手を擦り合わせるようにして息を吐いた。
「ちょっと寒くなってきましたね」
気が付けばカイロの温度もだいぶ低くなっている。
屋外と屋内の展示をなるべく交互に回るようにはしていたが、それでも冬の動物園は寒い。
一番獅子吼生と出会わないところをと言って選んだ場所だが、これで良かったのだろうかと隣を見ると。
「昆虫の展示もあるんですね。あそこに入ってもいいですか?」
「ああ、もちろん」
弾んだ声色で言われるので、不安は消えてしまった。
展示室の中に入るとあらゆる珍しい昆虫が目を引く。
蜘蛛などのいくつかの虫は彼女も引き気味に見てはいた。しかし蝶のコーナーはガラス張りの温室のようになっており、そこへ入ると彼女の目がぱっと輝いた。
「すごい、自由に蝶が飛んでるんですね」
そこは小さな庭園になっており、草木の間を自由に蝶が飛び回る。
青い翅が美しいアゲハ、小さくヒラヒラと舞う様子が可愛らしいシジミチョウの一種、変わった模様のセセリチョウ……彼女はそのどれもに小さな歓声を上げ歩き回る。
「確かに、これはすごいな」
彼女の背を追った俺も、多少ながら目は輝いていたと思う。
展示室の中は暖かく、外の寒さとは一転南国のようだった。その中で舞い上がる蝶はどこか幻想的で、別世界へ迷い込んだ気分になる。
「オオゴマダラ、シロオビアゲハ……」
近くに解説があったので、それと見比べながら名前を読み上げていく。どれも珍しい蝶ばかりだ。
その上こちらを警戒せずごく近くを飛ぶため、間近でその美しさを堪能することが出来る。
それに感動し目を奪われていると、隣にいたはずの彼女がいなくなっていた。
(いつの間に)
展示室には人影がなく、とても静かだ。
そんな中で彼女を見失うと、まるで無人の庭園にいるように思える。
名前を呼び返事を待つが、返ってこない。
(どこへ行ったんだ)
焦り歩き回るが、あっという間に半周してしまう。途中分かれ道もあったので、そこだろうかと戻るが見つからない。
(手を離さなければ良かった)
展示室に入る時、ドアを開けるために繋いだ手を離してしまっていた。そのまま繋いでいれば、慌てることもなかっただろうに。
(他に誰もいないせいだろうか。余計に不安になる)
妙な焦りを感じながらもう一度名前を呼ぶと、今度は返事がある。
「吉良先輩、こっちです」
やっと聞こえた小さな声にほっとするも、居場所が分からない。
あちこち見て回ってようやく、岩の影に隠れるようにして屈み込む彼女の姿を見つけた。
つづく

「こんなところに――」
そう声を掛けようとして、途中で言葉を呑み込む。
彼女が膝を折って見つめているのは、草に止まった蝶だった。
深い青の鱗粉は角度によっては銀にも光り、翅を上下させると残光のように目に色が残った。
(なるほど、それでか)
この蝶を驚かせまいと声を潜めていたのだろう。それならと同じように身をかがめ、静かに蝶を観察する。
「……綺麗だな」
「はい。飛び方もすごくキレイなんですよ。ちょっと待ってくださいね、きっと今に……」
囁くように会話をして、蝶の動きを待つ。
けれどいつまで経っても飛び立たず、草に留まって翅を休めている。
「……飛びませんね。疲れたのかな」
「そうかもな」
それからしばらく、じっと動かずにひたすら沈黙した。
たくさんの蝶が飛び交う中、俺たちは二人きりで呼吸さえ密やかに身を隠している。
それが不思議な気分だった。
(冬なのに暖かく、人の集まる場所なのに無人だ。俺たち以外は)
そのまま蝶の翅の動きを眺めていると、やがてふわりと飛び立った。
「あ」
「あ」
声が揃い、二人で目を見合わせる。
(……近い)
すぐ横に屈んだせいで、気が付けば肩が触れ合いそうな距離にいた。
きっと今なら、どんな吐息も声も聞き漏らすことはない。
「…………」
だからこそ何も言えず黙っていると、彼女も同じように黙りこくっていた。
「…………吉良、先輩」
まるで耳元で囁かれたみたいだ。
その声音が心地よく、無言のまま目を細めてしまう。
(もっと近くで)
抑えたはずの独占欲が、急に顔を出す。
(俺だけに、聞こえる声で)
他に誰もいない。誰も聞いたりなんかしない。
きっと、だからこそだ。なおさらコントロールが利かない。
(もっと近くにいてくれ。手を離さないでくれ――)
ケガをした利き手の甲で、そっと彼女の頬に触れた。その感触を確かめたくて、とっさに手が出てしまった。
(柔らかくて、熱い……)
わずかに戸惑いながらも俺を見つめる瞳に吸い寄せられそうになる。
けれど何か言いたげに彼女の目が瞬き、我に返った。
「――今の、蝶」
必死に言葉を探す。
「なんていう名前なんだろうな」
自分でもぎこちない話題のそらし方だと思うが、彼女は頬から離そうとした俺の手に、穏やかに自分の手を添えた。
「分からないけど……吉良先輩」
そして少しだけ照れたように視線を外しながらも、言った。
「手、使っちゃダメですよ。今日はこの手を……使わないように見張ってるんですから」
「ああ、そう、だな……」
思わず声が少しだけ上擦る。
頬に触れた手を止められて、その行き過ぎた独占欲を見透かされたようだ。
(そうだよな……お前は、俺のものじゃないのに)
思いのほか狼狽して手を引っ込めようとするが、なぜだか彼女は逆に手をつかんで離さない。
そして自分のもう片方の頬に、俺の手を触れさせて言った。
「ここ、温かいですね。顔すっごく熱いです。ほら」
はにかんで笑うので、その真意が見えない。
見えないが。
(ダメだ……)
このまま引き寄せてキスしたい。
その気持ちを振り払うために、同じように笑いながら立ち上がるしかなかった。
つづく

『暖かくなったらまた一緒に来よう』
それを今日の締めくくりにして、俺たちは別れた。
ため息を吐きながら家に帰り、買ってきた弁当を温めていると、何かあったのかと希に聞かれてしまった。
(こんなんじゃダメだな)
何もなかったと答えながら、またため息をついてしまった。
今日一日楽しかったし、彼女の新しい一面も見ることが出来てうれしかった。
大切な思い出になったと思うが、それでいて難しい心境だった。
(明日どんな顔で会えばいいのか)
会えば会うほど、愛しくなる。
引き寄せて、誰にも触れさせないように守り抱いて、唇を寄せたくなる。
夢を叶えてから想いを伝えよう。
彼女が困らないよう、もう少しお互いの気持ちが釣り合ってから伝えよう。
きっと今は、俺ばかりが彼女を求め、欲しがってしまっているから。
(でも……自制心にも限界がある)
それをまざまざと思い知った気分だった。
――動物じゃあるまいし。
我慢くらいするべきだ。自分で決めたことなのだから、想いの強さなんて関係ない。
しかし一方で、昼間の光景を思い出す。
(動物、か)
では比べてみたらどうだろう。
あのニホンザルの親子は、お互いを慈しみ、愛を持って接していた。彼らが出来ることも出来ないくせに『動物じゃあるまいし』だなんてよく言えたものだ。
(俺には、出来ないことが多すぎる)
希のことだって、今になってようやく前進した程度だ。それまでは家族から目を逸らし、逃げ続けて来たんだ。
彼女のことだって、『暴走』して止められる前に自分で気付くべきだったのだ。
(自分ばかり優先して……相手の気持ちに気付いてやれない)
至らないところばかり目について、ひどく落胆してしまう。
そんな調子で夕食の準備をしていると、希が俺の代わりに食卓に弁当を並べた。
「今日は俺が作ろうと思ってたのに。思ったより早く帰ってくるんだもんな、兄貴」
「……そうなのか?」
「そ。まあ買ってきてくれたんならそれでいいけど。明日は俺が作るから」
「そうか……ありがとう……」
しみじみと礼を言ったせいで、希が慌てる。
「いや、つーか! ケガしてる時まで夕食とか準備すんなよな!? 試験もあるんだし、俺が買うか作るかするに決まってんじゃねーか。それがフツーだろフツー!」
その狼狽ぶりに思わず苦笑してしまうが、乱暴な口調の裏にある思いやりが心に響いた。
(本当に……俺は兄と呼んでもらえるほどのことを、してやれているのか)
反省ばかりを繰り返してしまう。
けれどそう言ってもいられない、もうすぐ試験の日が来るし、それに落ちれば希望のレストランで働くことは叶わず、俺の夢も閉ざされてしまう。
なんとか気を持ち直し、試験に集中しよう。
何度もそう自分に言い聞かせた。
つづく

それから、月日は流れ。
たくさんの変化が俺に訪れた。
置かれた環境も、俺自身の気持ちも……
俺たちの、関係も。
「……結局、自分自身の力を見誤っていたんだな。俺はまだまだ未熟なのに」
「えっ?」
歩きながらそう呟くと、学ラン姿の彼女が目を瞬かせた。
卒業式の後、俺は彼女と話をしようと学校からの帰り道を二人歩いていた。
何をどう話そうかと頭の中で整理していたのだが、自分の不出来ばかり思い出してしまう。
「試験の時のことを思い返していたんだ。レストランへ向かう途中チンピラに絡まれて、お前と希が代わりに戦ってくれただろう」
もう数週間前のことだった。
試験を控えた俺を守るように二人は戦ってくれた。
その時の出来事が大きく俺を変えたし、おかげで試験も余裕を持って臨めたと思っている。
「あの時のお前たちの行動が、俺を救ってくれた」
「救うって……大げさですよ」
「大げさじゃない」
チンピラを撃退した彼女は、俺にこう言ってくれた。
『先輩の夢は、僕の夢でもあるんです。先輩の夢を応援したい。一緒にその道を歩きたいんです。だから、これからも先輩を守らせて下さい』
その言葉が、今も胸に残っている。
試験にも、彼女との関係にも焦りを感じていた俺を平静に引き戻してくれたから。
(あんなに一人で考え込み悩んでいたのに……いつも最後に救ってくれるのは、お前だ)
「守らなければと、ずっと思っていたんだ。大切な人は自分で守らないとこの手をすり抜けて失ってしまう。でも――」
そんな俺の言葉を聞いて、彼女は優しく微笑む。
「わたしも、吉良先輩を守ります。大丈夫です、いなくなったりしませんから」
焦る必要はない。
何もかもを背負い、自分で戦う必要はない。
それよりも俺自身が抱えた弱さを、迷いを、相手を信じて伝えた方がいいのだと、彼女は行動をもって示してくれた。
「……ありがとう、よく分かった。これから先困ることがあったら、真っ先にお前を頼りたい。それでいいんだよな?」
「もちろんです!」
その笑顔が、ますます俺を勇気づける。
そうして落ち着いて話せる場所に辿り着くと、そこは薄桃色の花が満開だった。
「桜がもう咲いてる……! キレイですね」
「ああ……春が来たんだと実感するな」
その桜の下で、俺は彼女に大切な報告をした。
レストランの試験に合格し、来週からパティシエの見習いとして働くということだ。
彼女はそれをまるで自分のことのように喜んでくれた。
その笑顔を、俺はずっと忘れないと思う。
(この先も永遠に、お前と喜びを分かち合いたい)
俺のどんな感情も、彼女は受け止めて正しい方へ導いてくれる。
もう一人で後悔しなくていい。
我慢も、しなくていい。
(お前はもう、俺に守られるだけの『妹』じゃない。俺の弱さも、受け止めてくれる……お前が居てくれて良かった)
思いの丈を話し、彼女に唇を寄せる。
今度こそ、優しく。想いを込めて。
(……頬が、熱い)
頬に添えた手からその温度が伝わってくる。
今度は彼女も俺の手を止めず、幸せそうに俺にすべてを任せてくれる。
その幸せは、俺と分かち合う幸福だ。
「……離れたくないな」
穏やかなキスの後、一度は身体を離したもののまた手をつかんでしまう。
出来ればずっと抱きしめていたかったが、何しろお互い学ラン姿だ。人気のない場所とはいえ、誰か通りかかったら困る。
「……えっと……わたしも、です」
その答えに口元が緩む。
どうしたものかと考えていると、彼女が先に口を開いた。
「あ、そうだ。わたし先輩に渡したいものがあるんです」
「渡したいもの?」
「試験に合格したら渡そうと思って、ずっと鞄に入れてたんですけど」
「ふっ。合格したらって……落ちたらどうするつもりだったんだ?」
「それは、合格するって信じてましたから!」
ますます笑ってしまう。
彼女はどこまでも愛しい。
「じゃあ……うちに来ないか。まだ一緒にいたい」
素直に伝えると、頷き返してくれる。
そのまま家へ向かったが、手を繋げずに歩く通学路がもどかしかった。
つづく

家に入り後ろ手にドアを閉めると、彼女と目が合う。
照れたように笑むのを見て、感情が振り切れてしまった。
「……っ」
その背に手を回しきつく抱きしめ、頭を抱えるようにしながら囁く。
「ありがとう」
真っ先に出てきたのがその言葉だった。
すると彼女は俺の腕の中でくすくすと笑う。
「……まだ、プレゼント渡してませんよ?」
「プレゼントの礼はまた後で」
「じゃあ今のは……?」
「それしか思いつかなかったんだ。お前と一緒にいる時間が……あまりに幸せで」
目が合って、引き合うように唇を合わせる。
二度目のキスは先ほどよりも熱を持ち、離れるまでに時間がかかった。
離れがたいと思って距離を縮めても、もっと離れがたくなっていくのが不思議だ。
(何をしてるんだか。こいつのことになると俺は全然冷静になれないな)
無理矢理思考を遮断して、その手を離す。
「……中へ入るか。プレゼントが何か気になるし」
言い訳のように話して、部屋の中へ入っていく。
彼女を座らせてお茶を淹れると、俺が戻る頃には包みを構えて待ち受けていた。
「はいっ、先輩どーぞ!」
「ありがとう」
二度目のありがとうを言いながら、包みを受け取る。感触が柔らかく、すぐに布物の何かだと分かる。
「開けてもいいか?」
「もちろん、いいですよ」
推測しながら包みを開けると、中から出てきたのはエプロンだった。シックな色で機能的な、デニム生地のものだ。
「エプロン……」
「家でたくさん使うんじゃないかと思って、丈夫なものにしてみました。料理の時もお菓子作りの時も使いますよね」
「そうだな。助かる」
立ち上がりそのエプロンを身体に当ててみる。背丈にもちょうど良く、使い心地も良さそうだ。
「似合いますね」
「お前の選び方が上手いからだ」
「えへへ。でもすごく悩んだんですよ」
「……ああ、そうだろうな」
俺自身もプレゼント選びで悩んだから、身に染みている。
そしてプレゼントを選ぶその間、俺のことをずっと考えてくれていたのだろう。
そう思うと、喜びは何倍にもなる。
「大切にするから」
心からそう言ったつもりだったが、やや自信なさげに彼女は俺を見上げた。
「……ちょっと実用的すぎたでしょうか。合格記念のプレゼントなら、もっと何か……思い出に残りそうなものの方が良かったかも」
「いや」
俺はすぐに首を横に振る。
「エプロンを着けている間は、いつでもお前を思い出せるから。これでいい」
彼女の横に座り、丁寧に畳んでテーブルの上に置く。
「一生大切にする」
「い、一生って。大げさですよ」
「大げさじゃない。大切にする。エプロンも……お前のことも」
また目が合ったので、その手を握った。
ぎこちなく指と指が絡み、手のひらをくっつける。
二人で体温を分け合うと、ぎゅっと心臓をつかまれた気分になる。
(幸せで、満たされているのに……それでももっとと思ってしまうのは、本当に我が儘だな)
その時、手を繋いだまま彼女が呟く。
「我が儘かもしれないんですけど」
声が出そうになるほど驚く。心の中を見透かされたのかと思ったが。
「――もう少し側に寄ってもいいですか?」
もう一度驚いてから、脱力する。
(何かと思えば)
「それが我が儘なのか?」
「だって。先輩と希くんの部屋ですし……希くんが帰ってきたら大変かなって」
「希は今日、相楽と遊んでくると言ってた」
「えっと、じゃあ……」
それ以上は言わずに、お互い沈黙し、次第に距離が近づく。
(……何度も瞬きをして)
緊張しているのか、連続で睫毛を上下させる。それでも俺を真っ直ぐに見て、唇をきゅっと結んでいた。
(可愛いな)
あと十センチくらいだろうか。
ふと彼女が目を瞑ったところへ俺も目を瞑り顔を近づける。すると鼻先が先にぶつかって、一緒に小さく笑った。
そして笑いながら、キスをする。
(幸せだ。お前と一緒にいると、俺の世界が変わっていく)
独りでいることも、我慢することも、大切なものを作らずにいることも、慣れていたのに。
今はもう、戻れない。
この手のひらのぬくもりが、俺を変えたから。
「戻りたくないな……お前がいなかった頃の自分には」
顔を離すのさえ惜しくて、彼女の髪が顔に触れるのを感じながら呟く。
すると今度は、可笑しそうに漏れる吐息が俺の唇にかかる。
「さっきも言ったじゃないですか」
重ねていた手のひらに体重をかけ。
先ほども聞いた言葉を繰り返した。
「わたしはいなくなったりしませんし、絶対に吉良先輩を守りますから」
――俺にそんなことを言ってくれる恋人は、世界でお前だけだ。
誰よりも特別な俺の彼女は、いつも俺に特別なものをくれる。
だから俺は、迷わず進んでいけるんだ。
お前と一緒の、未来へ。
終